こんにちは!ゆい先生です。
今日はこんなお悩み

絵本を読んでって言われるけど集中して聞いてくれないんですよね…

そうですよね!絵本ってただ読んでるだけじゃ子どもは飽きてしまったりするんですよ。
かく言う僕も先生になりての頃は絵本や紙芝居を読んでいる間に子どもが出歩いてしまったり、しゃべりだしたりしていました。
ですが今は絵本や紙芝居を読むと子ども達から「もう一回読んで!」と言われるほどになりました。
今回はぜひ僕が活用してるテクを皆さんと共有したいと思います!簡単に真似できますよ!
結論から言いますと…
の3つです!
では詳しくお話していきます。
子どもに絵本を読むときのコツ1 そのまま読まなくても良い
絵本によっては子どもに分かりずらい言葉を使っていたり、
自分の子どもには難しい言葉があったりする事ってありませんか?
例えば、「おばあさんは桃太郎にきびだんごをこしらえました」という文
このまま読むと

こしらえるって何?
となって集中がきれてしまうんです。
この場合は簡単に「きびだんごを作りしました」と言い直してもよいと思います。
そして、もう一つのコツはその文に無い言葉を入れる事です。
例えば
「そうだ!こうすればいいんだ!」というセリフがあったとします。
普通ならそのまま読むと思いますが…僕はこう読みます。

ん~…あ!そうだ!こうすればいいんだ!
普通何か思いつくときって「あ、そうだ!」と最初にあ!とか言いますよね?
そうゆう文にはないけど普通に話すときには出てくる言葉を入れると
一気にお話の中のキャラクターが現実味を帯びるのです。
子どもに絵本を読むときのコツ2 会話文は声を変えて読む
絵本の中のキャラクターが話す時「 」があってそこに言葉が書かれていますが
普通に読んだんじゃ楽しくありませんよね。
僕は男なので
女性なら裏声を使って、
ネズミ等小さな動物は高くて細い声を、
象やクマ等大きい動物は低くてゆっくり話し、
鬼や狼など悪者になるキャラクターは低めで怖い声を出して表現します。
これだけで子どもは一気に絵本の世界へ引き込まれます。
特にパパは声が低いので、怖い声を出すと迫力があってとっても面白いんです。
ママには出せない魅力があるのでとってもお勧めです!
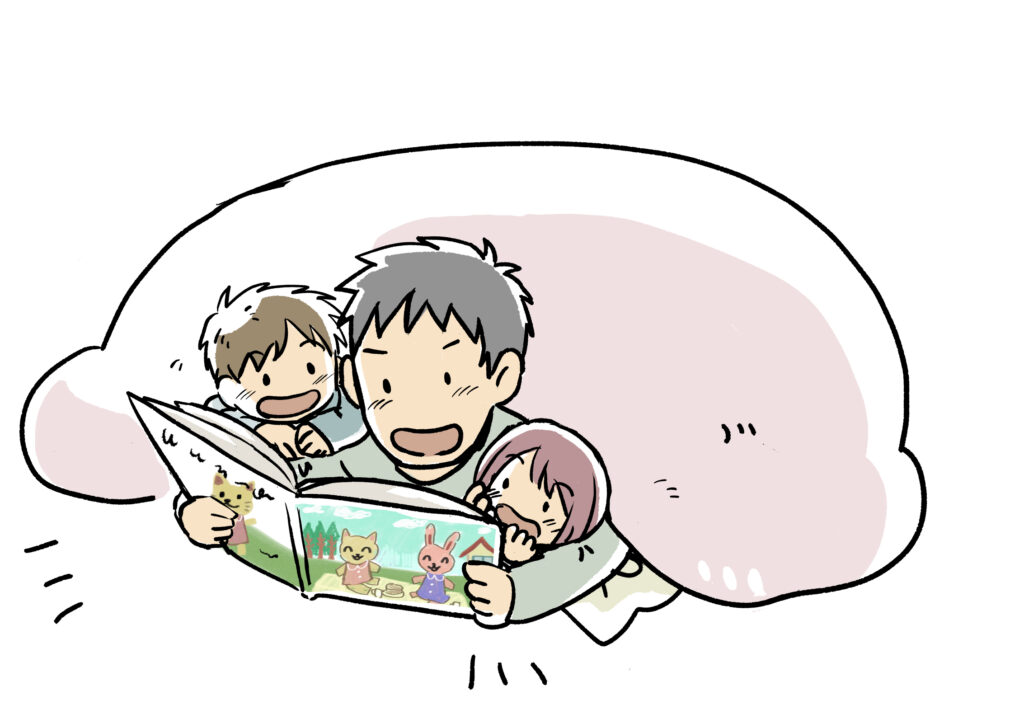
この方法のコツは事前に一度本を読んでおく事と役者になったつもりで恥ずかしがらずにやる事です。
ちゃんと予習しておかないとキャラクターを間違えて声を出してしまいます。
僕は間違えて狼の声でおばあさんのセリフを読んでしまったことがあります(笑)

子どもに絵本を読むときのコツ3 読むスピードを変える
絵本を読むときに淡々と同じスピードで読んでいませんか?
実は読むスピードも大事なんです。
例えば、大きなかぶのお話

かぶをおじいさんが引っ張って、
おじいさんをおばあさんが引っ張って、
おばあさんを孫娘が引っ張って…
と何回もこのフレーズが出てきます。この繰り返しが面白いお話です。
しかし、何度も読んでいると飽きてくる子もいます。
その時は読むスピードを速くします!
後半の分が長くなってきた所はわざと一息でめっちゃ早口で読むのです。
それを繰り返していくと子どもは

つぎはさっきより長いぞ…ママは言えるのかな…
とこのフレーズが来るのが楽しみになります。
そのフレーズの前に深呼吸して「いくよー」とか言いながら読むと
子どもも「頑張れ!」とか応援してくれたりするのです。
また、闘いのシーン等も少し早口で読むと緊迫した雰囲気を出す事が出来ます。
逆におじいさんやおばあさんのセリフはゆっくりに読みます。
早口のおじいさんやおばあさんはいないですもんね。
また、情景を知らせる文
「屋根はクッキー、扉はチョコレート、ドアには飴も付いています」(お菓子の家)
等はゆっくり読んでその風景をイメージ出来るように読みます。
子どもに絵本を読むときのコツ まとめ
いかがでしたか?そんなに難しくなかったと思います。
まずは恥ずかしがらずに役になりきってやってみるのが一番だと思います。
一度騙されたと思って声色を変えたり、話すスピードを変えたりして読んでみてください。
子どもの反応が絶対変わってくると思いますよ!
ぜひ試してみてくださいね!
この記事が少しでも役にたったら嬉しいです。
みなさまのお子さんとの時間が有意義になりますように!







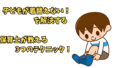




コメント